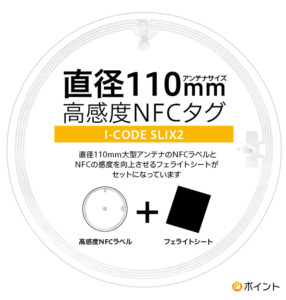ICカードって何?身近なFeliCaカードからキャッシュレス社会を学ぶ授業がスタート
私たちの生活の中にすっかり定着したICカード。とくにFeliCaカードと呼ばれる非接触型のICカードは、電車の改札を“ピッ”と通るあのSuicaやPASMOなどでおなじみです。
そんなFeliCa技術を使ったキャッシュレス社会のしくみを、中学生たちが楽しく学べる教育プログラムが、2025年度もスタートしました。提供するのは、ソニーとJR東日本。Suicaを支えるFeliCaの開発企業と、実際にサービスを運用している鉄道会社がタッグを組み、首都圏の中学校に無償で授業を提供します。
なぜICカード?なぜFeliCa?
このプログラムの特長は、単なるキャッシュレスの話ではなく、「ICカードに使われているFeliCaという技術が、理科の授業で習う“電磁誘導”とつながっている」という点。つまり、学校で学ぶ内容が実社会でどう生きているかを体感できるのです。
子どもたちは身近な決済手段を見つめ直し、グループワークを通じて、キャッシュレス社会のメリットや課題を多角的に考えます。FeliCaを使ったSuicaがどのようにお金のやりとりを可能にしているのか、目に見えない技術の仕組みにも踏み込みます。
未来のキャリアへもつながる学び
授業では講師が、FeliCaに携わる仕事のやりがいや、社会で役立つ技術開発の面白さについても語ります。技術を通じて人の生活を便利にし、社会の課題を解決していく。その姿に触れることで、子どもたちが将来のキャリアを考えるきっかけにもなるでしょう。
ICカードは単なる便利な道具ではなく、FeliCaカードをはじめとする非接触技術が社会の大きな変化を支えている存在。中学生にとっても、そのしくみや背景を知ることは、未来を切り拓く力になるはずです。